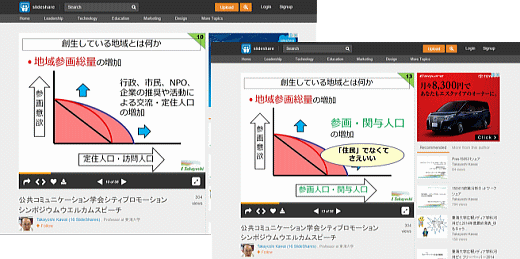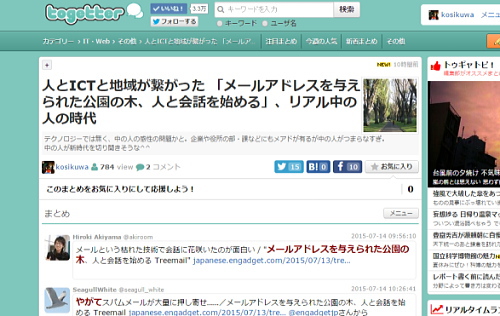メールアドレスを与えられた公園の木、人と会話を始めるという記事をみつけたアダプトプログラム関係者は膝を打ったでしょう。
アダプト・プロフラム、の周知・発展に結び付きそう、はたまた地域参画総量の増加にも・・・。
メルアドだけでも面白いですが、ここはひとつツイッターやフェイスブックなどのアカウントを持たせて「見える化」も可能にすればさらに面白くなり、地域参画総量の増加に結び付くと思います。それが最終的には地域創生・地方創生に結び付くのでは・・・。
※ 地方創生とは: 国内の各地域・地方が、特徴を活かした自律的で持続的な社会をかたちづくること。地域振興・活性化などを指し、、農業、観光、科学技術イノベーションなどさまざまな起点が地方創生のあり方として想定されている。
その辺を
1、メールアドレスをもらった公園の木
2、アダプトプログラムとは
3、住民参画・地域参画総量
4、ICT・SNSによる拡散・視覚化
という順番で調べます。
1、メールアドレスをもらった公園の木
この記事です・「メールアドレスを与えられた公園の木、人と会話を始める」
公園の木が会話を始めるまでの経過の要約
●公園の木が痛んでいる
↓
●行政が・担当者が困る(調べきれない)
↓
●市民に助けてもらおう報告してもらおう(東海大河井教授は確か「弱さを見せる・市民に助けを求められる強い行政」というような事を言われていたような) → そうだ、解り易く・効率よくするために木毎にメールアドレスをふろう。
↓
●市民からは木そのものに宛てて健康状態を案じるメール・悩み相談・ラブレター・政治談義まで数千通が届く事態
↓
●心の有る担当者が返事をするようになる 中の人の誕生
↓
●公園の木の管理への市民参加が・・・
さらにこうして世界的なニュースにもなり公園の木を見てくれる人が増えたのではないでしょうか。
当局は「中の人」の手間だけで目的を達成、さらに市民の公園への関わりを引き出しました。
市民の手だけで公園の木に関する問題解決なんてことも出てきそうです。
これってアダプトプログラムっぽいですよね。
2、アダプトプログラムとは
アドプトプログラム、アダプトシステムとも呼ばれる。
●Wikipedia:アダプト・プログラム・・・一定区画の公共の場所を養子にみたて、市民がわが子のように愛情をもって面倒をみ(清掃美化を行い)、行政がこれを支援する制度。
●長野県:アダプトシステム・・・自治体と住民がお互いの役割分担について協定を結び、継続的に美化活動を進める制度です。1985年、アメリカでハイウェイのボランティア清掃活動として始まりました。
都市部・都会的センス、市民に開かれた市の一覧の感がありますね。
3、地域参画
歩道や公園の管理に市民が入ることにより、市民自らの手で解決してゆくことが期待できます。
筆者も家の後の用水の管理道路を近所と一緒に管理草取りしています。
これは、メール一本で市に提案しただけのもので、契約・予算無しで勝手にさせてもらっています。
芝を植えたり、花を植えたり、撤去に困るような構造物や木を植えたりしない限りOKということでやっています。
ただし、これだと他の人に見えません。
地域の活性化や交流人口・参画人口・参画意欲を第三者が見ることはできません。
ここでやはり先にご紹介した「地域参画総量」が出てきます。
地域参画総量とは
東海大学の河井孝仁教授が提言されている考え方。
資料スライド:公共コミュニケーション学会シティプロモーションシンポジウムウエルカムスピーチ
このサイトでまとめたもの
本当に地域に係わるにはまず身近の町内への自主参加(つきあい・やらされる では無い)自分の自由もきくアダプトプログラムがスタートです。
こういうところで自主性に火をつけないと、イベント等もただの動員・人数・数値になってしまいます。
地域参画総量の大事ポイントは「参画意欲」です。
これさえ守れば自由にしてよいよ、ということになれば自分の気持ちを歩道や公園に反映させいつくしむようになりますし。草ぼうぼうは恥ずかしくて、草取りも頑張るようになります。
4、 ICT・SNSによる拡散・視覚化
さらに、「メールアドレスをもらった公園の木」のようなことはSNSでさらに容易になります。
フェイスブックの例をあげます。
下記記事は、公園で見かけたことに関して発信したものです。
・左がトンボの名前の問いかけ・・・(答えが寄せられ名前どころか学名まで解りました)
・右が枯れそうな木を発見して何かの病気ではないかと問うているもの・・・今時点で病気は解っていませんが「いいね」で拡散協力されています。
この記事はこれを書いた個人のタイムライン以外に、この公園のタイムラインにも自動表示されます。
この公園に関心がある人・訪問者と共有されるのです。
後日談:この木の病名は私がネット上で見つけました。
地域の観光アカウント(一般的に市町村が運営)がもっとも活発な情報発信を行っているので対策を取られているか聞いてみました。(FB上で)
すると、「既に公園を管理する業者は把握しており対策中」とのことがFBだ返ってきました。そこで、公園のページにも記入される方法で「支所がすでに対応している」FBに書き込みました。
これで、同じく心配に思った人は公園ページを見て安心できます。
これはまさに地域参画とその視覚化です。
- 公園訪問
- 写真付き記事アップ
- 知合い・知らない人からの公園への関心を引き起こす。
- 行政介在せずに1つは解決(トンボの名前、さらに群生地であることも写真付きでわかり、別展開の可能性も)
- 枯れそうな木の情報は市民の手で拡散中、市民で解決できるか(放っておいてよい場合)、管理者側に伝わるか、既に手が打ってあるのかそういうことも解ると良いですね。
- 地域参画総量の拡大(この公園に係わった人がかなり増えました)
ということで「メールアドレスもらった公園の木とアダプトプログラムと地域参画総量」
アダプトプログラム(住民参画) → ICT・SNS → 地域参画総量増加・視覚化 → 地域創生
きっとこれが地道な努力方向だと思います。
「付き合い・やらせられる」から自主・自由、市民に任せる(行政が口を出さない)で一気に変わると思いますが。
最後にtogetterまとめ「人とICTと地域が繋がった 「メールアドレスを与えられた公園の木、人と会話を始める」、リアル中の人の時代」もチェックしてみてください。