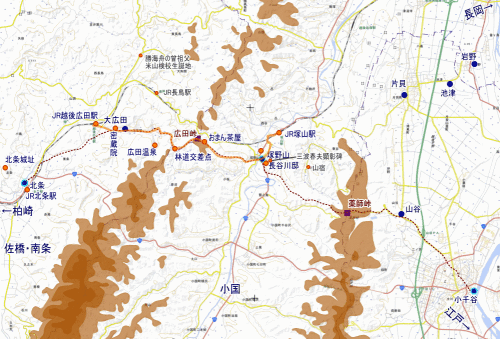[素人歴史妄想シリーズ]
いよいよ北条からの街道、広田峠に挑みます。
まず最初にこの街道の呼び方について
この街道の名称は色々ありまして、柏崎・刈羽側では小千谷街道、小千谷・魚沼側では高田街道と呼ばれ、中間の塚野山では魚沼街道と呼ばれているようです。
ここでは中をとって塚野山の魚沼街道と呼びます。
盛り沢山の街道・峠道ですので前編・中編・後編と3回に分けて書きます。
前編の目次
- 今回のルートの概要
- 越後広田駅から広田温泉分岐、舗装道終了までのレポート
- 街道の呼び名について
という流れで行きます。
1、ルート概要
北条から小千谷までの間のうち、越後広田駅から塚山駅まで歩きました。
上杉謙信も、もちろん景勝も直江兼続も馬で越え、ひょっとすると山県有朋(柏崎から小千谷に行ったとすればここを通ったことが濃厚だが別ルートだったかな?)も越えたかもしれない峠です。
地図は全て国土地理院の地理院地図、電子国土Webから利用させていただいています。
小千谷には信濃川の船着き場河戸が有り魚沼にも長岡・新潟にも通じていました。
塚野山には渋海川の河戸が有り長岡や小国へ、北条にもその地形から鯖石川の支流長鳥川の河戸があって柏崎につながっていたのではないかと思います。
2、越後広田駅から広田温泉分岐、舗装道終了までのレポート
前編はこの地図のように広田地内を歩いた分です。
寄り道、撮影しながら約1時間くらいでしょうか。
1、電車利用できます
この峠道が今も整備されていれば「電車利用で気軽に歩けるルート」としても紹介できるように電車で行きました。JR信越本線越後広田駅で降ります。
2、越後広田
これが越後広田駅、無人駅です。なぜか実家のお寺さんはこの広田に有ります。小さな時にこの駅で降りて歩いていった事があったはずです。
3、北条(きたじょう)コミセン
本来北条(隣りの駅)が中心の旧北条町ですが、越後広田は旧北条町の地理的中央に位置しており、コミュニティセンターが置かれています。中越地震・中越沖地震で被害を受けましたが、しっかりした地域で住民の力で組織的に支え合い、乗り越えたそうです。それらの縁で神奈川県藤沢市六会地区との交流が防災グリーンツーリズム等で継続しています。
4、峠への街道に入ります
この交差点を右に折れるといよいよ大広田、峠への道です。
5、沢の中へ
沢の中へ向かって道が延びます。
6、交差点
長鳥方面からの道と合流します。右が峠方面
7、お寺の案内石柱
交差点から直ぐ先に密蔵院への坂道の入り口に石柱が建っています。
8、門と鐘
坂道の脇から急な石段、門の上に鐘が有ってその下をくぐる不思議な入口。
真言宗、密教です。チベット当たりの異国情緒を感じました。(ちょっぴりラマ教は密教的な部分もあるとか。)
9、密蔵院本堂
屋根の木材が新しい感じ、修復が成されているようです。
10、石碑と石像
弘法大師(空海)様の石像だと思います。
像の右手前の小さな灯篭みたいなものにお賽銭の口が有ります。
旅の無事を願って投入しましたよ。(実はそれで峠道でご利益ありました)
11、広田神社
密蔵院の隣りが広田神社への石段
12.広田神社2
これが広田神社、リンク先の解説によりますと、色々な神社を合併してあるようです。
広田の広という字ですが、大江広元(毛利家の始祖)の広元のうち広を越後毛利(北条高広等)、元を安芸毛利(毛利元就等)が引き継いだという話が有ります。この広田の広もその系統の広ではないかなとひそかに期待^^ ついでに気が付いたのですが大広田、なんで大がつくのか疑問なんですが、大江広元の田んぼ、を縮めればあらら大広田なんすよね。どうでしょ? ちなみに大江広元(おおえのひろもと)は源頼朝の側近中の側近、守護地頭制度、征夷大将軍の仕組みを作ったとも言われる鎌倉幕府官僚の筆頭です。その方の領地に北条も含まれていたのでした。いかに重要な地であったのかわかってね^^
12、街道に戻る
峠への街道に戻り大広田集落を歩くと石仏様?の祠
ちゃんと花が活けて有ります。
13、さらにゆくと
やはり祠が有りました。こちらは斜面にコンクリートで埋め込まれています。ここもちゃんとお花。
もちろん全てにお賽銭をあげました。まさかこんなにいっぱいあるとは思わず、小銭になってしまった神仏様、ごめんなさい。
14、ゆっくりと上り坂
大広田は緩やかな上り坂になています。沢の北側、つまり山並みの南斜面を道がゆっくり上ってゆきます。この位置にあると雪が早く融けるので雪国ではこの道の付け方が必須です。(新しい道路で反対側に道路をつけた峠(小千谷市の旧桜町峠等)が有りますが、おそらく雪を知らない技術者の手による設計かと。後に角栄さんが桜町峠を見て怒った逸話「なんで北斜面に道路をつけたんだ」が残されています。)その左右上下に家が有り、それぞれ下り道か登り道がついています。
ということで、大広田が峠への街道沿いに発展した集落らしいことが解ります。
15、湧き水
歩みを早め大広田集落も終わりかけたころ、コンクリートの側面の管から湧水が出ていました。おそらく崩れないように工事したものと思われます。昔は多くの旅人がここで水の補給をしたことでしょう。
16、分岐
さらに進むと峠への道(左)と広田温泉への分岐が見えました。
広田駅からここまで58分。途中、寺と神社で8分くらい使ったので、真直ぐ来ればゆっくり歩いて50分くらいでしょうか。
17、広田温泉
しばらく進むと眼下の道奥に広田温泉らしき建物が見えました。
広田温泉は湯治場で、鉱泉で温度は低いですが温めてあり結構人気のある温泉です。
今は湯本館のみの営業のようです。
18、舗装の終わり
さらに登ってゆくと、いよいよ舗装道路も終わり、未舗装の道へとなり林道・山道となります。
中編は尾根の林道へ到達、遠く越後三山の眺め、広田峠、おまん茶屋史蹟などの紹介です。
3、街道の呼び名について
その呼び方から「それぞれから見た街道の使われ方」がなんとなくわかります。
柏崎・刈羽郡「小千谷街道」: 柏崎からはひとまず小千谷に抜ける街道ということでしょうか、その先は三国街道・信濃川船道があり魚沼・江戸方面もあれば長岡・新潟方面も有るという立場でしょうか。さらには会津方面も有ったでしょうか。
小千谷・魚沼郡「高田街道」: 昔、魚沼地域は高田藩領で年貢・物産(からむし・反物等)、そして奥只見の銀山でとれた銀を高田まで運ぶ街道。(※銀山街道ともよばれ、そうよんだのはは高田藩かもです。)
塚野山・(三島郡?)「魚沼街道」: 塚野山宿を通行・投宿したのは魚沼の人達が多かったのが想像できます。鈴木牧之の北越雪譜に何度も塚野山付近の話、渋海川の話が出てくるのです。鈴木牧之は今で言う南魚沼市塩沢の商人です。最高級品、カラムシや織物を大消費地の京と全国物流の大阪へ送るルートとして関東市場の清水峠等と並び最も重要な街道峠道だったと思います。塚野山宿にとってのお得意さんが魚沼人だったのでは?