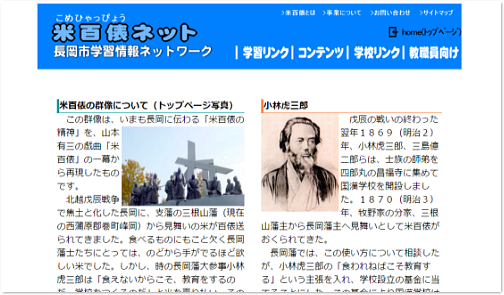越後長岡の戊辰戦争から明治維新にかけての故事「米百俵」
世界にまで広がりました。
教育への1つの考え方を、世界を造り始めています。
発展途上国時代の日本と同じく世界のこれから発展してゆく若く元気な国に伝わっているようです。
きっかけは、ドナルドキーンさんの英訳からのようです。
1868年:戊辰戦争の北越戦争で長岡藩敗れる。
1869年:小林虎三郎、三島億二郎らは四郎丸に国漢学校開設。
1870年:牧野家の分家、三根山藩主から長岡藩主へ見舞いとして米百俵が届く。
同年:その米百俵を学校設立の基金とし、一等地への移転、より充実した教育を開始。(参考:米百俵ネット)
1943年:山本有三の戯曲「米百俵」発表 「山本有三の米百俵誕生秘話」(小千谷市慈眼寺のHP)
1996年:日浦長岡市長がドナルドキーンさんに「『米百俵』を翻訳し、世界に伝えてほしい、と懇願」 One Hundred Sacks of Rice(米百俵)(柏崎市)
1998年:”One Hundred Sacks of Rice” 山本有三・戯曲「米百表」を Nagaoka City kome HyappyoFoundation より翻訳刊行。
2000年代初期ホンジュラスにて演劇が上演される。なんとその具体的な記述・資料がネット上に存在せず。なんなんでしょ。
YOUTUBEの動画だけ貼っておきます。
国旗の重み 教育編~ホンジュラスの米百俵~
関連、中米の米百俵 「「米百俵」海を渡る」(PDF) 元ホンジュラス大使 竹元正美
「エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカでも上演されました。」
バングラディシュにて米百俵の上演?これまた不明です。
長岡市のサイトにバングラディシュの米百俵賞受賞の紹介はありますが具体的な記述は有りません。
森市長のブログに記述が有りました。
戯曲米百俵を公演しているシルパカラ・アカデミー劇団(バングラデシュ)に米百俵賞を贈呈
平成18年3月、国際交流基金の活動の一環として、日本から京都「すわらじ劇園」木村進次氏がバングラディシュを訪問、戯曲「米百俵」を紹介したことをきっかけに、ドナルド・キーン氏の英文翻訳をベンガル語に翻訳し、アカデミーのゴラム・サルワー氏が脚本・監督し舞台劇に仕立てました。 20120619-2_kome100.jpg シルパカラ・アカデミー劇団は、同年8月に初めて公演を行ったのを機に、芸術院に属する若者が「米百俵」を上演する劇団として特別に立ち上げた劇団です。
市長自ら率先して情報を流されています。
こうやって米百俵は様々な人の力で世界に広がっていたのです。