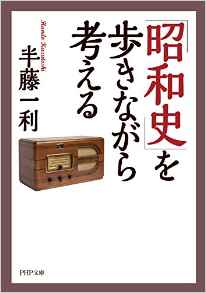リアリズム、常識、半藤一利さんの著書の周りにある堅めの言葉。
誰もが避けている日本の歴史の真実を追求した半藤さん。
読みやすいのですが重い言葉がどうしても多くなります。
でも、疎開していた父親の郷里、半藤さんの祖父母の家、その辺のことを書くとき記述は柔らかな言葉が多く、半藤さんの心情が出ています。
以前、何かで読んだのは「雪の田舎で物凄い難儀をした。」という風な事。
田舎に良い記憶はない・・・半藤さんにとってはそうなのかな。
と思っていましたが。
2015年3月に発売された PHP文庫「昭和史」を歩きながら考える を読んでそれは全く違うのだと気づいたところです。
読んでいて半藤さんの人柄に触れて感動して涙がこみ上げました。
というより泣いたのですが。
とにかくこの【「昭和史」を歩きながら考える】は傑作だと思います。
群馬県桐生市で坂口安吾と酒を飲み歴史を学ぶシーンから始まって
新潟県長岡市の雪に埋もれた岩野村の祖父母の家の炬燵で野菜と鮭でお酒をちびちびとやる。
そのシーンで終わっています。
最後の件は涙無しでは飲めないですね。
半藤さんはこの雪国を愛し、食と酒を心底愛していたようだ。
祖父母の家は孫にとってだいたい天国なんですがね。
2つの書籍から半藤さんの人となりと疎開の雪国と岩野についてまとめたいと思います。
- 昭和探偵 昭和史をゆく・・・・岩野の半藤氏について
- 「昭和史」を歩きながら考える・・・各コラムを見てみます
- 岩野の半藤さん
1、昭和探偵 昭和史をゆく・・・・岩野の半藤氏について
珍しい苗字「半藤」
第十四話 九段坂の上の雲 二百六十万の死者
のなかの 1、名誉の戦死はありえない の中にこうあります。
延歴二十年(ブログ筆者注:西暦801年)、坂上田村麻呂の東国征伐の折に従った武士に半藤宗正という人が有りまして、帰途越後を通ったとき・・・・田村麻呂が持っていた千手観音の木像の守護せしめるため宗正ら数名をその地に留めた・・・
そう言う記録が「新潟県中魚沼郡誌」にあるそうで、つまり征夷大将軍の家来の半藤宗正が祖先らしいとの事です。
司馬遼太郎さんに半藤さんが話すと「そんなのは作り話に決まっている」と一蹴された話をどこかで読みました。
好きな事を言い合う仲だったようです、半藤さんと司馬さん。いいですね。
それはさておき、確かに半藤という苗字は他の地域にはありません。
このへんで半藤と言えば岩野の人と決まっています。
それで、新聞に「長岡市の半藤」が出てまとめたのが
全国バレーボール大会主将に半藤姓、それで半藤一利さん(山本五十六他著書多数)を調べた経過と調査報告
です。
このバレーボールのキャプテン半藤さん、まさに岩野の方でした。
半藤さんは戊申の役から日清日露、第一次大戦まで忠魂碑が作られ名前が刻まれているのに対し、太平洋戦争の膨大な戦死者の正確な人数も名前も確認されていない事を半藤姓の戦死者を調べる中で改めて愕然としたようです。
下記写真は岩野の小学校跡地前に有る忠魂碑、碑の裏に戦争毎の戦死者名が有るが(半藤姓も数名有り)、太平洋戦争の戦死者の名前は無い。
2、「昭和史」を歩きながら考える・・・各コラムを見てみます
第1章 「昭和史」のなかのわたくし
昭和28年(P10)
- 文藝春秋新社就職
- 坂口安吾担当となり、1週間泊まり込む、酒と歴史を教えられる。
- 安吾「人間はそう簡単に変わるもんじゃない・・・またぞろわれら日本人は世界に冠たる優秀民族だなんて、獅子吼する人間がいっぱい出てくるに決まっている」
- 若者達は花と散ったが、同じ彼らが生き残って闇屋となる。
- このリアリズム!戦後日本をどういう国につくり直すのか、皆目見当はつかないが、安吾直伝のリアリズムだけは我が精神に叩き込んでおかねばならぬ、・・・
- 安吾は我が師
第4章 歳時のコラム
雪の守るもの(P290)
- 東京大空襲で家を焼かれ、やむなく新潟県長岡市の寒村で、昭和20年夏から3年間を過ごしたから、わたくしも雪の非情さ、始末の悪さを身にしみて承知している。
- 人に諦めと待つことを教えて、雪は降る。
- 次の時代のため、日本文化の原始性と自然の美しさと有難さとを、雪は温存していてくれるのであるという。
思い出の味(P292)
- 雪がしんしんしんしんと降る夜なんか、炬燵にもぐっていいこんころ持ちになり、冷たい果物や野菜のありがたさを知った。茄子の歯ざわりの締り、ポリポリした胡瓜、白菜、それに柿、とくに密柑である。・・・・・まこと、冬は食べ物を美味とする。
- それと鮭である。「今日は御馳走らて」と前宣伝があれば・・・・甘塩のアラマキのときもあれば、塩を多く使ったシオビキのときもあった。・・・
- 身欠き鰊の味も忘れられない。カチンカチンの鰊を・・・少し柔らかくなったのをコブ巻きにするか、野菜と一緒にするか、・・・
- 二日も三日もゴトゴト、グズグズと飽きずに煮る。これを肴に炬燵にぬくまって越後の酒をチビリチビリ・・・
ところところの抜き出しですが、いかに半藤さんが雪国越後を愛し、冬の食とお酒を堪能していたか。
私は最後の数コラムを読みながらジーンときました。
是非購入されて読んでみてください。
3、岩野の半藤さん
下記は岩野の神社、ここで盆踊りも行われたはずですし、背も高く男前で勉強も出来て、地元の旦那様の家柄の一利さんは周辺の村娘の憧れだったと思います。でも、普通の家の娘では手の届かない存在だったのではないでしょうか。
後に半藤さんは長岡中学の後輩と結婚します。文学界に深く係わられた血筋の方です。
半藤さんの一生の伴侶は長岡中学に居たのです。
「昭和史」を歩きながら考えるの最後の最後、岩野の炬燵と食と酒の件に出てくるのはその彼女だと思います。