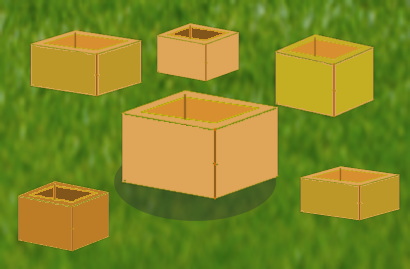NHK大河ドラマで、秀吉が秀次や石田三成に「検地とは?」と尋ねるシーンがあり、いろいろの問答の末、主人公の真田幸村が「全国で異なるますの大きさを統一しましょう」ということで落着。
私もそういうことだと思っていました。
が、ネットで調べてゆくうちに違うことが判明。
「はは~ん、日本てそういう国なのね。鎌倉・室町と来て、戦国から安土桃山・江戸という流れってそういうことなのね」と、わかった気がしたのでメモ。
1、太閤検地
その前にまずはWikipedia 太閤検地
太閤検地の成果は、権利関係の整理や単位統一・・・農民への年貢の賦課、大名や家臣への知行給付、軍役賦課、家格など、その後の制度、経済、文化の基礎となる正確な情報が中央に集権・・・
戦国時代の日本では、個々の農民が直接領主に年貢を納めるのではなく、農民たちは「村(惣村)」という団体として領主に年貢・・・
升は京升を使う。・・・
戦国時代までは農村側が自己申告・・・太閤検地では多くの田畑が実際に計測された
とのこと
2、時代考証の先生のツイート
で、真田丸の検地のシーンが面白かったのと、家族で評判になったので検索してみたら専門家のツイートを集めた興味深いサイトを発見。
それが
【「真田丸」第15話 太閤検地についての時代考証の先生のツイートまとめ】
このサイトでは、
丸島和洋 @kazumaru_cf 日本中世史、戦国時代の研究者です。大河ドラマ「真田丸」時代考証。
という方のツイートを上手にまとめられています。
どうぞお読みください。
でその中にある。1つの重要なツイートがこれです。
秀吉の太閤検地の特徴は、全国の「公定計算枡」を京枡に統一したということでした(他の度量衡もいじってますが)。これは、あくまで豊臣政権が把握する数字です。独自で検地を行っていた大名(毛利や真田)は、従来のやり方を踏襲し、豊臣政権に報告する際に換算をしていました。
— 丸島和洋 (@kazumaru_cf) April 17, 2016
全国の「公定計算枡」を京枡に統一した
独自で検地を行っていた大名(毛利や真田)は、従来のやり方を踏襲
この部分ですね。
各国の通貨で申告されても統計されてもわからない。全部ドルに換算して数字を出してくれ。
と、いうことなんですね。
3、京枡はドル
ドルの立場が「京枡」
なので、各地は今まで通りの枡を使っていたわけです。
枡の大きさが統一されたのではなく、公定計算枡が決められたということが正しいようです。
換算すればすぐに京枡でどのくらいなのかがわかるのです。
どうやらそうみたいです。
ということで、日本は地方の力が強く、農民の力も強く、その地方の独自性を認めながらも全国的に通じる方法を決め告知したということですね。
4、戦国武士政権の合理性
おそらく、そういう道理、合理性を始めたのは信長で、それは当時の武士たちの領地経営に欠かせない合理精神だったように思います。
それに対抗するのがまだしぶとく残っていた公家や寺社のあいまいな領地と搾取。
ですので、途中で公家や寺社に近いといわれた明智光秀が信長を倒しても、同じ路線を掲げる秀吉に大勢がついたのは当然なのでしょう。
おそらく、家康も秀吉と同じく合理的な領地経営を願う大名や領主に担がれた政権。
だから武家諸法度や公家や寺社の法度も作って武士の権利・合理を実現していったように思います。