編集長の岩佐十良氏はフェイスブックでこの5月号のオススメとして
Talk about the future 連載 第7回 テーマ:「移住」と「地方の未来」を考える。
をあげ3人のゲストを紹介しそのさわりも掲載してくれました。それが貴重なものに見えたので買い求めました。
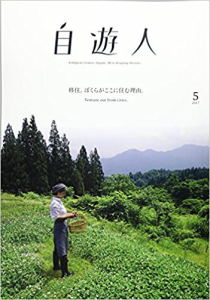
買ってみると「「移住」と「地方の未来」を考える。」も、もちろんよかったのですが、この号のテーマ「移住。ぼくらがここに住む理由。」がめちゃ面白かった。
何人もの長いレポートも一気読みでした。
雪国の人でも田舎のこの自然の恵みをよく理解できる人はそんなに多くはないです。
雪を嫌なものと思っている人の方が多いです。
この本の特集に出てくるひとのお話に出てくるのは
- 通勤が通勤では無くまるでドライブ、常に山や里の景色が違う。
- 意外でしょうが東京に居た時よりも芸術に触れて暮らしている。
- 会社の裏山でバックカントリーが出来る。
- 山菜採りや畑仕事の中にしかない喜びがある。
- 縄文時代から続く人の営みが続いている。
- 北越雪譜の世界
- 図書館が素敵
一方でもちろん不便な点も挙げています。
で、さらにこの本では
★里山十帖で働いている人に聞きました 「地方に住んでわかった 好きなところ 嫌いなところ」
20名のコメントが書かれている、それぞれ物凄く個性的です。これも読んでいて楽しい
さらに
★「自遊人の暮らし」&「自由人」で働いている人に聞きました 「地方に住んでわかった 好きなところ 嫌いなところ」
15名のコメントが書かれている、これもまた物凄く個性的です。これも読んでいて楽しい
つまりこの号は「里山十帖」&「自遊人の暮らし」&「自由人」で働いている人達が明らかになった楽しい号だったのです。
これはファンの方は買いです、もちろん。
地球の恵み山菜
この特集を読み終えて雪国の田舎人として思いを巡らすと、本来あらゆる動物は採り放題食い放題の環境で繁栄していること、山菜採りはそれを経験できる、何も植えたり世話したりしていないけど地球は恵みを用意してくれる。
ただひとつ気を配っているのは採りつくさないこと。だから次の年もちゃんと同じくらい生えてきます。
いま思えば日本の漁業は根こそぎ魚を捕りつくして再生できずに滅びつつある状況みたいです。
山の民と海の民は違いますね。
鈴木牧之北越雪譜と自遊人・里山十帖
それと多くの人が触れた北越雪譜・鈴木牧之、「雪国の暮らしを誰も本当に江戸に伝えていないから自分がやった」それが江戸時代のベストセラーを生んだ背景です。自遊人・里山十帖とまるで同じですね。
遠くカラムシの時代から越後上布の時代まで、とにかく物凄く長い間日本の最高級の布の産地だったわけで南魚沼・十日町はかなり豊かな地域だったと思います。
参考:越後の超高級繊維カラムシを調べていたら鎌倉幕府、大江・毛利から謙信、幕末までの謎解明。
参考:北越雪譜は江戸時代のシティプロモーション?観光と物産と誇り喚起の宝の山?
1837年に江戸で発売されてベストセラーになってから今年でちょうど180年。
この号で雪国越後の素晴らしさが発信されました。
(※ バックカントリーの素晴らしさの特集と魚沼の写真家のミニ写真集も掲載されています)
