小千谷市には浮世絵がいっぱい有ってひな祭りの時にお雛様と一緒に展示している。
で、浮世絵は中越地震の時にかなりの枚数が破棄されたという話も聞きました。
そこで、
1、小千谷のひな祭りってどのようなもの(浮世絵の展示は)?
2、なぜ小千谷は浮世絵王国なのか?
と調べてみます。
1、小千谷のひな祭りってどのようなもの(浮世絵の展示は)?
ネット上の情報ページにリンクしてみます。
★小千谷のひな祭り(小千谷市)

このひな祭りの特長部分を引用させてもらいます。
小千谷には、ひなまつりに「ひな人形」を飾った部屋の壁一面に絵紙(浮世絵)を飾る風習があります。…
…楽集館では「小千谷に伝わる浮世絵展11」が開催されおり、今回は武者絵を中心とした展示が行われています。…
…和順会館には江戸から明治にかけて刷られた浮世絵が約630枚飾られており、…
なんかスゴイ文化があるようですね。知りませんでした。
★絵紙で彩る小千谷のひいなまつり:浮世絵に囲まれたひな祭り(新潟観光ナビ)

★ひな飾り、浮世絵で彩る 小千谷の風習を再現(新潟日報)

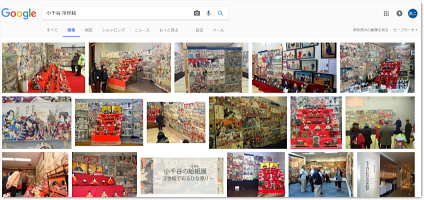
2、なぜ小千谷は浮世絵王国なのか?
どうして小千谷に浮世絵がいっぱいあるのでしょう?
小千谷の歴史にその秘密があるようです。
ここでもやはりWikipedia先生から引用させてもらいます。
小千谷の流通に関する歴史
- 続日本紀には西暦702年頃に魚沼郡の存在を記している。
- 市内一部は南魚沼市の一部、魚沼市、旧川口町を含む藪神荘という荘園であった。
- 1553年 – 上杉謙信が朝廷にこの辺りで生産されている越後布を献上した。
- 1578年 – 御館の乱が起こり、平子氏は景虎方につき、ひ生城は景勝方に攻め滅ぼされる。…このころ青苧などは、南魚沼地区や中魚沼地区から魚野川や信濃川で小千谷に下り、陸路で柏崎の港に運ばれていたとみられる。
- 1611年 – 三国街道開通。
- 1620年 – 信濃川が氾濫し大洪水になる。
- 1638年 – 街が元町から現在の段丘上(本町)に移転する。
- 17世紀 – 堀次郎将俊が越後麻布から小千谷縮に改良し、小千谷縮の生産が始まる。
- 1681年 – 当市域の多くは幕府直轄領(天領)になった。
- 17世紀後期 – 江戸へ小千谷縮が売り出され、元禄には京、大阪にも売り出される。
- 1763年 – 会津藩が預り地として管理した。同藩は小千谷陣屋を置き、魚沼郡内の藩領と合わせて支配した。
- 1837年 – 北越雪譜(鈴木牧之)が江戸で出版される。
- 1868年 – 戊辰戦争(北越戦争)では、小千谷も戦場となった。長岡藩の家老である河井継之助と新政府軍の岩村精一郎との会談が慈眼寺で行われた(小千谷談判)。
- 1887年 – 旭橋開通。
- 1911年9月14日 – 魚沼鉄道(後の国鉄魚沼線新来迎寺(後の来迎寺駅)~小千谷(後の西小千谷駅)間開通。
- 1920年11月1日 – 国鉄上越北線(現上越線)宮内~東小千谷開通。
- 1927年 – 飯山線が越後川口駅~十日町駅間開通。
- 1931年9月1日 – 上越線全通。
- 1931年1月9日 – 小粟田原に中越飛行場がつくられる。
- 1955年 – 小千谷縮が国の重要無形文化財に指定される。
- 2004年10月23日 – 直下で震度6強の地震が発生(新潟県中越地震)。
さらに「小千谷縮(Wikipedia)」からも引用
小千谷の縮の全国との関係
- 17世紀中頃、小千谷で縮市が開かれるようになった。魚沼・刈羽・頸城で織られた縮が小千谷の仲買人・問屋に集められた。他に、堀之内・十日町でも縮市が開かれていた。
- 『越後名寄』には、「4月から7月迄行われる縮市には、江戸・京・大坂など日本中の商人が集まっていた」と書かれている。
- 1800年の『北越志』には、「大きな家も、小さな家も、民家は一軒残らず機織の音のしない家はない。皆、縮を織っているのだ。」と書かれている。『北越志』の著者が越後を訪れたのは夏の頃で、織りの最盛期ではなかったが、それでも、多くの家が機織していたという。
- 寛政の改革(1787年)、天保の改革(1842年)で、高級品の売買や使用を制限されたため、縮問屋や生産者は大損害を受けた。
さらに下記を調べてみます。
にいがた人模様:小千谷絵紙保存会事務局長・横山久一郎さん /新潟
上記サイト他から浮世絵が小千谷に集まったのは
「江戸時代末期から明治時代にかけて、織物商人が江戸の土産として持ち帰ったもの」らしいです。
さらに上記の横山さんのお話ですとこういう流れになります。
中央大文学部の鈴木俊幸教授(日本近世文学専攻)らが調査に訪れた。
↓
危機感を持ち、専門家らと一緒に保存会を設立。
↓
調査結果をまとめた冊子を各戸に配布。
↓
2004年の中越地震
↓
平成商店街協同組合と協力し、絵紙の風習を再現したひな祭りイベント「絵紙で彩る小千谷のひいな祭り」を開催
この中であらためて浮世絵の価値を知るに至った中央大文学部の鈴木俊幸教授の研究についてYOMIURI ONLINE に有りましたので是非お読みください。全貌が解ります。
小千谷の浮世絵についてその由来から詳しく書かれています。
これを読めば小千谷の浮世絵・絵紙について理解が深まるでしょう。
で、現在1万5000枚以上の浮世絵が小千谷市内にあるそうです。
スゴイですね。
小千谷港を中心とした小千谷縮は大きな富をもたらし、おそらく日本有数の浮世絵収集の文化も花開いていたようです。
次のひいな祭りには行ってみたいですね。

